2023年度の「Miraijuプロジェクト」は、「創業100周年プロモーション」と「従業員満足度向上・DE&I推進」という2つのテーマを事務局で設定し、取り組んでもらいました。末嶋さんと室賀さんは、異なるチームでの活動でしたが、ともにサブリーダーというポジションで活動されていました。それぞれ、選んだテーマと参加したきっかけをお聞きできますか。


「Miraijuプロジェクト」参加者座談会
プロジェクトを通じて生まれる種が
やがて会社を支える大樹になる。
Miraijuプロジェクトとは
大樹生命の将来を担う若手社員による部署横断型プロジェクト。
2016年度より毎年開催し、2023年度は8回目。
各年度の研究テーマに関して、チーム毎に提言をまとめ、経営層への発表を行う。
-
 人事部
人事部
人事企画グループ- 神宮 一貴
- 2014年入社 総合政策学部 卒
2023年に現在の部署へ異動し、今回初めて「Mirajuプロジェクト」の企画運営を担当するほか、人件費管理なども担当。
-
 業務推進部
業務推進部
業務推進グループ- 末嶋 佑樹
- 2019年入社 経済学部 卒
業務推進グループの計画チームに所属し、支社・営業部の業績目標をはじめとする目標策定や、目標達成に向けた推進策の立案などを行う。
-
 企画部
企画部
経営企画グループ- 室賀 大世
- 2020年入社 経済学部 卒
年度計画の遂行や中期経営計画の策定に向け、ホールセール部門との窓口を担当するほか、社内コミュニケーション活性化に向けた業務なども担当。


2023年度のテーマ&参加したきっかけ
日常の業務では体験できない
成長のチャンスをつかみにいく。

神宮

末嶋
私が参加したテーマは「創業100周年プロモーション」で、チーム5人で議論を重ねつつ、提言内容をまとめていきました。参加を決めた理由としては、大樹生命の大きな歴史の1ページになるであろう「100周年」という取り組みに対して、普段の業務とは違うアプローチで考えることが、自分の成長に繋がると思ったからです。また、最終的に役員へ提言するということで、「そんな機会はほかにない」と魅力を感じて、挑戦しました。

室賀
実は私は、昨年から2年連続での参加でした。選んだテーマは「従業員満足度向上・DE&I推進」。昨年も参加して、普段接することのない所属部外の社員と交流することで、自分の考え方や知識が広がり、成長につながることが大きく実感できたので、今年も参加しました。

神宮
室賀さんが「従業員満足度向上・DE&I推進」というテーマを選んだ理由は何ですか?

室賀
「従業員満足度向上・DE&I推進」を選んだというよりも、逆に「創業100周年プロモーション」は私がいる企画部がこれから取り組んでいく領域でもあるので、せっかくならば日常の業務で携われないことを、と考えこちらを選びました。

末嶋
私も神宮さんに聞いてみたかったのですが、今回の2つのテーマは、どんな意図があって設定したんですか?

神宮
2023年度の研究テーマは、中期経営計画の最終年度だったことを踏まえ、全社視点での課題をテーマにしたいと考えました。まず、「創業100周年プロモーション」は、2024年度からの中期経営計画の最終年度(2026年度)に、大樹生命が創業100周年を迎える年度であったこと。また、「従業員満足度向上・DE&I推進」は、企業の持続的成長に必要な要素であり、若手社員にとって身近に感じられる課題であることを踏まえ、設定しました。


最終発表で行った提言
深く考え抜いたことが伝わる、
渾身の最終提言。

末嶋
最終発表では、「創業100周年プロモーション」というテーマに対して、対従業員と対お客さまという2つの観点からそれぞれ若者に対するプロモーション案を提言しました。対お客さまでは、当社が50年間にわたり行っている「苗木プレゼントキャンペーン」を若者向けにSNSを絡めた形で強化し、新たに「大樹グリーンプロジェクト」と題して打ち出す案、対従業員向けでは、経営層から若手社員へ、会社のビジョンや思い描く未来像をより具体的にイメージしてもらう共有の場として、「Tフェス」という大規模な100周年イベントを開催する案を出しました。

室賀
私はちょうどコロナ禍での入社で、なかなか会社で大規模なイベントや集まりができない世代だったので、「Tフェス」という発想を聞いたときには純粋にワクワクしました。

末嶋
内容的にも、イベントの企画などを中心に若手が活躍できる場を増やす予定でした。たまには、若手中心に盛り上がる場があってもいいだろうと(笑)。

室賀
ぜひ、実現してほしいです。私たちのチームでは「従業員満足度向上とDE&I推進」に向けて、まず従業員満足度が「働きやすさ」と「働きがい」の両軸から成るものだと捉え、それぞれの観点からよりよい職場環境作りへの取り組みについて提言しました。具体的には「ワークライフバランスのさらなる向上」「若手がいきいきと働けるよう全方位的な支援・サポート体制の構築」です。今も充実はしていますが、さらに体制を整えていきたいという提案です。

末嶋
若手にとって心強く、モチベーションが上がりますね!

神宮
最終発表を聞いて、本当にすばらしい提言だったと思いますし、両チームとも役員から「期待を超えてきた」というコメントもいただきました。私から見ても、とくに今年は会社課題に対しての掘り下げを、しっかり行っていたのが伝わってくる内容でした。発表を聞いていても課題から解決策へと結びついた経緯がわかりやすく、同世代として「確かにそう思っていた」と納得する場面がいくつもありました。
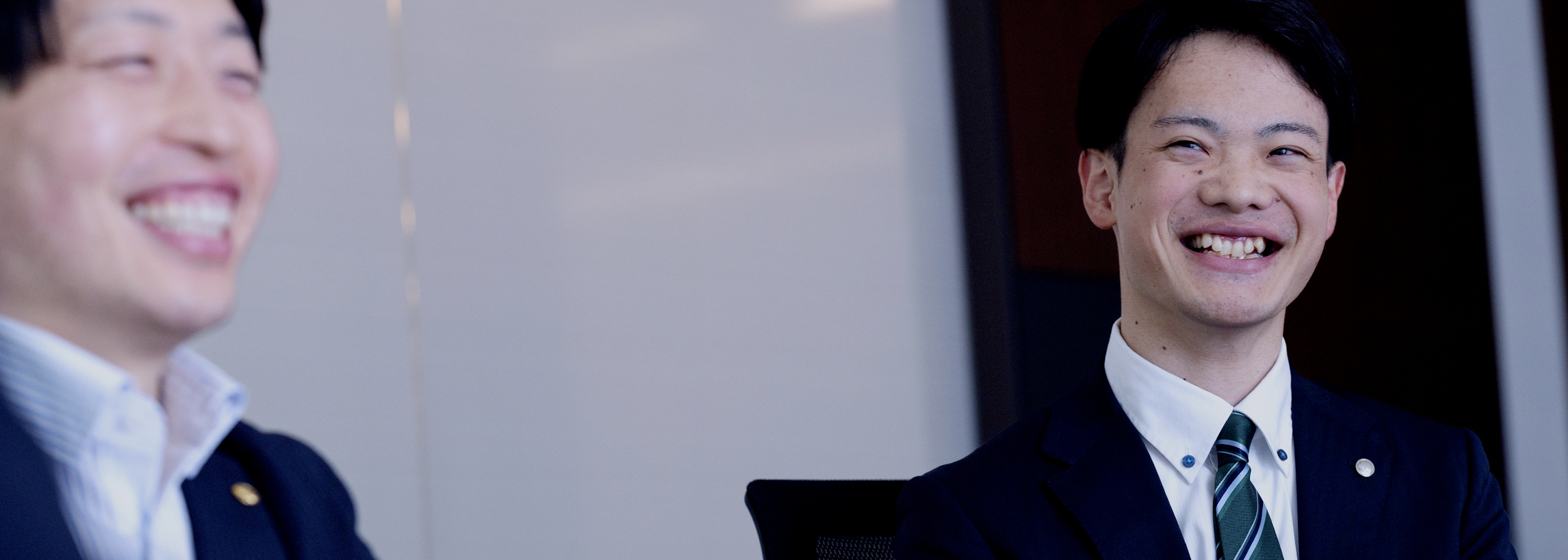

プロジェクトを通して感じた自身の成長
チームの議論の場を活性化させつつ、
最終的な提言の内容にもこだわり抜く。

神宮
改めて今回のプロジェクトを通じて、どんな経験が学びになったと感じていますか?

末嶋
私のチームは5人で、とくに新卒1年目の後輩が2人いたこともあって、議論の活性化と、意見の集約というところに注力しました。誰かが発言したらかならずリアクションを取るようにし、発言しやすい環境を作る。また、チームの目指す方向をつねに意識しながら議論をうまく導く。ミーティングのたび、集中力が必要でしたが、その分意見を引き出す力とまとめる力、ファシリテーターとしてのスキルは、すごく成長できた部分だと感じています。

神宮
末嶋さんのチームは、それぞれの勤務地が全国に散らばっていたので、すべてリモート会議で進めていましたよね。うまく役割分担をしながら、ミーティングごとに次回までの宿題を設定して、スムーズに進めていたのが印象的でした。

室賀
私のチームでも、最初は周りの意見を聞いていることが多かった後輩社員が、最後は積極的に意見を出すようになり、その成長を見て私もまた刺激を受けました。また、昨年も参加した身からすると、今年一番の学びになったのは、外部講師の方に、提言をまとめる際のプロセスや思考、進め方を教えていただいたことです。研修・ワークショップで学んだことを、プロジェクトですぐに実践できるので、経験的に身に付けられる実感がありました。問題点の把握から解決策の考え方まで、ロジカルに組み立てられるようになったのは、業務にもかならず活かせるスキルだと思います。

末嶋
確かに課題を分析する力、考える力、言語化する力といった部分が、終えてみると自分でも大きく向上できたと感じますよね。

神宮
「そう言ってもらえると、企画者としても外部講師を招いたワークショップを開催してよかったなと感じます。2022年度も、経営層への中間報告会を導入し、2023年度に踏襲されているので、「Miraijuプロジェクト」自体がどんどん新しい取り組みをしながら成長し、若手がもっと大きく成長できるプロジェクトに進化させていきたいですね。


終えてみて感じる、
Miraijuプロジェクトの意義
仲間同士で高め合い、
大樹生命を導く人材へと成長する。

末嶋
今回、初めて「Miraijuプロジェクト」に参加しましたが、入社1年目から参加できて役員に提言する機会もあると思うと、ものすごく成長できる機会を与えてくれるプロジェクトですよね。今後もっと参加者が増えてプロジェクト自体が盛り上がり、会社を良くする人材がどんどん育っていくプロジェクトになっていくのではないかと思います。

室賀
私は、2年連続で参加してみて、やはり自分が大きく成長できる機会であることと、業務が忙しくても挑戦する価値が十分あると、改めて感じました。あとは他部署の従業員との交流が生まれるのも魅力ですよね。「Miraijuプロジェクト」で広がった人の輪は、日々の業務にもかならず活きてきますし、それをきっかけに従業員同士が高め合う風土がさらに広がっていくと思います。

神宮
ありがとうございます。「Miraijuプロジェクト」の意義は、大樹生命の将来を担う人材を育てていくことにあると考えています。その中で、個人的なスキルだけでなく、多様な人と仕事を進めていく力など、様々な力を身につけてほしい、というのが企画者側の思いです。今後も、一度参加したOBがプロジェクトに関わっていく機会を増やして、今以上にMiraijuプロジェクトを通じた繋がりが広げていきたいと考えています。ここから生まれた種が、いつか芽を出し、やがて会社を支える大きな樹になるように、より多くの方に意義を感じてもらえるプロジェクトにしていきたいですね。


