「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」を踏まえた当社取組状況について
2024年6月27日
大樹生命保険株式会社
1.はじめに
生命保険協会は、生命保険各社がお客さま一人ひとりに真摯に向き合い、社会的使命を果たし続けることを後押しするために、2023年2月17日に「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」(以下「着眼点」)を取りまとめ、2024年4月19日に「着眼点」を更新しています*1。
当社は、経営理念に則った「お客さま本位の業務運営」を実践していくことで、コンプライアンス・リスク管理態勢の継続的な取組強化・高度化を図ってきております。更なる高度化に取り組んでいく上で、「お客さま本位の業務運営」の取組状況と併せて、「着眼点」に記載の6つの項目、16のプリンシプル(原理・原則)に対する当社取組状況を公表します。
2.当社取組状況
(1) コンプライアンス・リスク管理態勢
〈「着眼点」の記載内容(生命保険協会より)〉
「コンプライアンス・リスク管理態勢」は、各社の業務運営の基礎となる組織体制の構築や企業文化の形成等を指す。営業職員チャネルの特徴・強みであるお客さまとの強固な信頼関係に応え変わらぬ安心をお届けしていくためには、目指す理念や価値観の共有、実効的な統制策を遂行する強固な組織体制の構築等、健全なコンプライアンス・リスク管理態勢の整備・維持が求められる。
○当社では、経営理念として、相互扶助の精神にもとづく生命保険事業の本質を自覚し、その社会的責任を全うするため、「まごころと感謝の気持をもって、常に契約者に対する最善の奉仕に徹する」旨を掲げ、お客さまにお約束した保険金・給付金等を確実にお支払いすることを通じて、お客さまの生活の安定と向上に寄与するべく努めてまいりました。また、当社で働く全役職員が共有する価値観である「大樹生命バリュー(*)」に沿った行動を心がけ、お客さま本位経営やコンプライアンスの重要性について、経営陣が管理者・従業員一人ひとりに直接語りかけ続けることで、コンプライアンス・リスク管理態勢を維持してまいります。今後も、コンプライアンス・リスク管理に関する経営陣の考え方を示し、その趣旨を浸透させるよう取り組んでまいります。
〈これまでの主な取組み〉
プリンシプル① 経営陣の姿勢・主導的役割
- 経営陣が従業員に対し、お客さま本位経営の推進やコンプライアンスの重要性について自らメッセージを発信するとともに、毎年、支社を訪問し、営業部の管理者等を含む従業員との意見交換等を実施し、その趣旨を伝えるよう取り組んでいます。
プリンシプル② 営業組織における管理者の役割
- 支社・営業部の管理者の責任・権限を規程にて明確にし、経営陣が、定期的に支社・営業部の管理者に向けて、それぞれに期待する役割を説明しています。
- 支社管理者はコンプライアンス責任者として、自支社の課題を把握した上で「コンプライアンス推進計画」を策定し、コンプライアンスの推進を図り、営業部管理者は営業部のコンプライアンス管理者として、支社管理者の監督のもと自組織のコンプライアンスの推進に向け取り組んでいます。
プリンシプル③ より良い企業文化の形成に向けた取組み
- 全役職員に「経営理念」、「行動規範」、「大樹生命バリュー」等を掲載した常時携帯のコンプライアンス・カードを配付し、一人ひとりが常に正しく職務を遂行し、お客さまのBESTパートナーとして信頼されるためにコンプライアンスの実践を図っています。
- 経営陣が毎年各支社を訪問する機会を設け、「お客さま本位」の行動の重要性を語り掛け、その理念の浸透を図ると共に、支社・営業部所属員から「お客さま本位」を実現する為の意見の収集・交換を行い、現場と本社が一体でその高度化に向けた取組みを行っています。
プリンシプル④ 「三線管理態勢※2」の構築
- 1線として営業組織を管理・指導する営業統括部門(コンプライアンス指導を担う専管組織を設置)、2線の視点からの1線指導を含むコンプライアンス推進を行うコンプライアンス部門、1線・2線との協働・連携と改善提言を行う3線の内部監査部門から成るコンプライアンス・リスク管理態勢を構築しています。
- 第三者的立場にある社外取締役を含む取締役会等、経営陣に対する牽制機能が働くガバナンス体制を構築しています。
(2) コンプライアンス・リスクの評価
〈「着眼点」の記載内容(生命保険協会より)〉
「コンプライアンス・リスクの評価」は、自社の事業における固有のリスクや、防止すべき不適正事象の影響度・頻度等について、適切に評価することを指す。それぞれのリスクに応じた適切な態勢を構築するコンプライアンス・リスク管理の考え方においては、各社にて営業職員チャネルの特徴や自社の特性等に応じたリスクの評価がなされることが求められる。
〇当社では、全社共通の「コンプライアンス・プログラム」を策定するとともに、支社ごとに特性・課題が異なることから支社単位の「コンプライアンス推進計画」を策定し、コンプライアンス部門がフォローすることとしています。今後も、支社ごとのマーケットの特性や固有の課題等に応じたリスクの評価が適切に行われるよう、「コンプライアンス・プログラム」および「コンプライアンス推進計画」に基づく取組みの高度化を進めてまいります。
<これまでの主な取組み>
プリンシプル⑤ コンプライアンス・リスクの評価
- 「内部統制システムに関する基本方針」および「コンプライアンス規程」に基づき、全社共通の「コンプライアンス・プログラム」を取締役会にて策定し、コンプライアンス部門が「本社コンプライアンス会議」において取組状況を定期的に確認・フォローしています。その結果は、経営会議および取締役会に報告しています。
- 支社においては、全社共通の「コンプライアンス・プログラム」をもとに、自支社の特性・課題を踏まえた支社単位の「コンプライアンス推進計画」を策定し、定期的にPDCAを実施しています。
(3) コンプライアンス・リスクに対するコントロールの整備・実施
〈「着眼点」の記載内容(生命保険協会より)〉
「コンプライアンス・リスクに対するコントロールの整備・実施」は、統制環境やリスク評価にもとづく、コンプライアンス・リスク管理上の具体的な統制策に関する取組みを指す。営業職員チャネルにおける不適正行為の防止のためには、前述のリスク評価の結果も踏まえた強固な統制策の整備・実施が求められる。
○コンプライアンス・リスク管理上の具体的な統制策については、過去の不適正事象の分析に基き、コンプライアンス・リスクが認められる場合の契約取扱の制限や営業職員の指導・管理に関する仕組みを構築し、さらなる高度化に取り組んでいます。引き続きコンプライアンス・リスクに対するコントロールの高度化を目指すとともに、営業職員に対するコンプライアンス教育等を徹底してまいります。
〈これまでの主な取組み〉
プリンシプル⑥ 業務ルールの明確化
- 不適正行為を生じさせないために、「マナー・コンプライアンスマニュアル」を作成し、業務ルールや禁止行為を明示するとともに、当社以外の業務(以下「副業」)に従事する場合は当社への申告を必要とし、年度始には当社が禁止する副業(当社が業務上取り扱う商品以外の金融商品の勧誘・紹介行為等)に従事していないことを確認する誓約書を取り付ける等、リスクの低減に向けた取組みを行っています。
- 営業職員が直接の金銭授受を行わない業務フローを構築するとともに、当社ホームページやお手続き書類において、「当社職員が現金をお預かりすることはない」等のお客さまに対する注意喚起を図っています。併せて、営業職員に関する金銭トラブル等の予兆把握およびその管理を行っています。
- 70歳以上のお客さまのお申込み手続き時には、ご親族の同席を必須とし、特にお子さま世代の同席を優先し、ご親族の同席が困難な場合には営業組織の管理者である営業部長等がご親族等に確認する取組みを行っています。また、社内ルール上、必須としている80歳以上のお客さまに対する複数募集人説明・複数回説明について、70歳以上のお客さまにもお願いするなど、ご加入の意思・理解状況をしっかりと確認させていただくよう努めており、お申込み手続き後にご不明点の有無などを改めてお電話等にて確認させていただいています。
プリンシプル⑦ 教育・研修
-
お客さま本位・法令遵守の徹底の観点から、「マナー・コンプライアンスマニュアル」による月2回の研修を実施すると共に、全営業職員を対象に毎日「お客さま本位」研修を実施することにより、お客さま本位に基づいた行動やコンプライアンスを前提とした適正な保険募集ルール、アフターサービスの定着を図っています。
-
営業組織の管理者である営業部長に対して、実際に発生した不適切事案をもとにしたコンプライアンス研修を実施しています。
プリンシプル⑧ 人事・報酬(表彰)制度
- 営業組織の表彰制度や管理者の評価においては、お客さま本位の活動を評価する指標のウェイトを高くし、不適正行為による法令・社内規則違反等の発生には減算を行う規程としており、営業目標への結果だけに評価が偏らないような仕組みとしています。
- 営業職員の表彰規程においては、お客さま本位の活動とともに、成績優秀者の高潔性を踏まえた評価をするために、不適正行為があった場合には表彰を取り消す規程を設け、厳格な運行を行っています。
- 営業組織の管理者である営業部長の異動・配置に際して、コンプライアンスに関する情報がある場合は、人事部門がコンプライアンス部門の見解を確認の上、人事案を決定しています。
プリンシプル⑨ 営業職員の活動管理
- 営業組織の管理者である営業部長は、営業職員と日々活動面談を実施することにより、活動量等の定量実績とお客さまとの会話から得られる定性情報を確認し、お客さまに合わせた個別指導も含め、活動の管理を行っています。
- 営業職員の活動実態を踏まえて、コンプライアンス・リスクが懸念されるケースで契約取扱を制限する仕組みや、コンプライアンス・リスクが懸念される営業職員を検知して指導・管理する仕組みを構築しています。
(4) コンプライアンス・リスクのモニタリングおよび不適正事象の(予兆)把握時の対応
〈「着眼点」の記載内容(生命保険協会より)〉
「コンプライアンス・リスクのモニタリング」は、自社におけるリスク評価やコントロールの状況を含む、自社のコンプライアンス・リスク管理態勢の整備・機能状況の監視を指す。新型コロナウイルス感染症の感染拡大やデジタライゼーションの進展等に伴うリモート環境下での活動機会の増加等、環境の変化によりリスクの状況や統制策の実効性等も変化しうるものであり、実効的なコンプライアンス・リスク管理態勢の維持のためには、コントロールを通じて得られる不適正事象の(予兆)情報も含め、適切なモニタリングの実施が求められる。
○不適正リスクが高いと考えられる契約に対する牽制等により、不適正事象の(予兆)情報についてモニタリングを実施しています。また、実際に支社・営業部等で不適正が懸念される事象が確認された際には、コンプライアンス部門において案件を一元管理し、原因究明や再発防止策の実施等を行っています。引き続き営業組織への牽制を含めた不適正事象の未然防止取組に努めてまいります。
〈これまでの主な取組み〉
プリンシプル⑩ コンプライアンス・リスクのモニタリング
- 営業統括部門、コンプライアンス部門にて、不適正リスクの懸念がある契約の取扱いをシステム的に制限するとともに、高齢のお客さま等十分に確認が必要な契約に対して、営業職員以外の第三者による電話での手続確認を行っています。
- コンプライアンス部門より営業職員に関するリスク懸念項目のデータを支社に毎月提供しています。支社では共有・対応策を協議する会議を毎月実施し、モニタリングを行うことで不適正事案の未然防止、予兆把握に努めています。
- 金銭関連の不適正事象の予兆把握・防止の観点から、一定の要件を満たした取扱いに対し、本社から電話による手続き確認を実施しています。
プリンシプル⑪ 不適正事象の(予兆)把握時の対応
- 営業組織において、不適正な取扱いの恐れのある事象を把握した場合は、速やかにコンプライアンス部門へ報告することとしており、営業組織がコンプライアンス部門の指示に基づき、適切な事実確認を行います。また、重大な異常事象懸念(不祥事案、情報漏洩、事件・事故等)が判明した場合は、詳細確認や対応策検討を待たずに、速やかに経営陣等へ報告することとしています。なお、不適正事象が判明した場合には、営業組織は、原因分析や再発防止策を講じ、コンプライアンス部門が再発防止策の実効性の確認を行っています。
- 不適正懸念が残る営業職員に対しては、支社ごとに管理規程を設け、支社内で情報を共有するとともに継続的な注視を行い、不適正な事象を未然に防止する運行を実施しています。
(5) コミュニケーション
〈「着眼点」の記載内容(生命保険協会より)〉
ここでいう「コミュニケーション」とは、必要な情報が適時適切に、社内外の関係者に伝達されるための管理態勢および日常業務における取組みを指す。社内環境等の要因によるコミュニケーションの不足は、不適正事象の抑止・発見の阻害要因ともなり得ることから、社内・社外(お客さまや各種ステークホルダー等)との適切なコミュニケーションが行われる環境や態勢を構築することが求められる。
○社内外での日常業務において、適切なコミュニケーションが図られるよう各種取組を行っています。今後もより一層の風通しのよい企業風土の形成に向け、取り組んでまいります。
〈これまでの主な取組み〉
プリンシプル⑫⑬ 社内におけるコミュニケーション
- 営業組織における円滑なコミュニケーションがなされる環境を整えるために、全営業職員に対して管理者とのコミュニケーションの状況についてのアンケートを毎年実施し、その結果を管理者にフィードバックすることで、自己を客観的に振り返り、改善に取り組める仕組みを構築し、課題が見られる管理者に対しては、本社から直接指導・フォローを実施しています。また、全従業員に対して、意識実態を把握するためのアンケートを実施・フィードバックしています。
プリンシプル⑭ 社外とのコミュニケーション
- お客さまから営業拠点やコールセンター、当社ホームページに寄せられた声、アンケートの結果等は「お客さまの声」としてお客さまサービス部門で一元管理・分析を行い、適切なサービスの提供に向け取り組んでいます。また、不適正リスクのある申出等に関しては適切に対処しています。
プリンシプル⑮ 内部通報制度
- 内部通報制度として、コンプライアンス部門を窓口とする社内通報・相談窓口のほか、弁護士事務所による社外通報窓口や日本生命グループ共通窓口(日本生命内)の設置など幅広く受け付ける態勢を構築しています。
- 内部通報制度の周知に努めるとともに、通報者への不利益な取扱いが無い等、通報者保護を徹底し、安心して通報・相談ができる環境を整備しています。
(6) 監査
〈「着眼点」の記載内容(生命保険協会より)〉
「監査」部門は、三線管理態勢において、営業組織等の業務部門(1線)・コンプライアンス部門(2線)のコンプライアンス・リスクに関する態勢や取組みが適正かつ有効に構築・実施されているかの検証を行い、改善につなげる役割を担っている。営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢が実効的に整備されるにあたり、監査部門が営業職員チャネルの特性や自社を取り巻く環境等を理解し、役割を発揮していくことも求められる。
○監査部門が機能発揮するために、各分野での知見を有する人材の配置を行うとともに、事前のデータ分析によるリスク事案の絞り込みを行い、効率的かつ実効性のある監査を実施しています。今後も有効な機能発揮に向け、1線・2線組織との連携強化等に取り組んでまいります。
〈これまでの主な取組み〉
プリンシプル⑯ 監査
- 監査部には、部長・支社長経験者をはじめ社内の各分野での知見を有する人材を配置し、監査関係資格(CIA等)の取得促進、営業・コンプライアンス関係を含む社外セミナーの受講等を通じて、監査担当者の監査スキル・知識の向上に努めています。
- 外部の豊富な知見を有する社外取締役・社外監査役には、取締役会・監査役会にて定期的に監査計画ならびに監査結果の報告を実施し、より客観的な立場からの意見を確認しています。
- 監査計画の策定にあたっては各業務分野において想定されるリスクに対するモニタリング、役員へのヒアリング、内外のビジネス環境変化等を踏まえ、取組方針やテーマ監査候補の選定を行っています。
- 営業組織の監査実施時には、各支社の課題と改善策を提言するとともに、監査部による定期的な改善フォローを行うことで実効性の確保を図っています。
3. 終わりに
以上の通り、「着眼点」に記載の6つの項目、16のプリンシプルについて、概ね取り組んでいることを確認しています。全役職員が「大樹生命バリュー」を意識した「お客さま本位の業務運営」を実践し、コンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化を図るために、「着眼点」に記載の各種取組例を参考にし、継続的な取組を進めてまいります。
以上
(*) 大樹生命バリュー
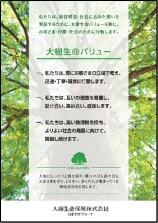
一、私たちは、常にお客さまの立場で考え、迅速・丁寧・誠実に行動します。
一、私たちは、互いの個性を尊重し、助け合い、高め合い、成長します。
一、私たちは、高い倫理観を持ち、よりよい社会の発展に向けて、挑戦し続けます。
*1生命保険協会「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」の更新および公表について
https://www.seiho.or.jp/info/news/2024/20240419_2.html
*2営業組織等の業務部門(1線)、営業組織への牽制・支援等を担当するコンプライアンス部門(2線)、1線・2線の有効性に対する監査を担当する内部監査部門(3線)から構成される態勢
