2030年には65歳以上の約3人に1人が認知症または軽度認知障がいになると推計されています。認知症は誰もがなり得るものであり、ご家族が認知症になることなども含めて、多くの人にとって身近なものになっています。
認知症の予防に取り組んだり、認知症になった場合に備えるためには、正しい知識と十分な情報が必要になります。大樹生命は、認知症に関する最新の情報をお届けいたします。
認知症の新たなリスク=目の老化 『アイフレイル』とは?
視力の衰えが新たな認知症のリスクを高めることが示されています。
加齢による目の衰えや目の病気による目の症状は、初期は自覚症状として現れにくく見逃されがちです。
健康な状態と視覚障がいの中間である「アイフレイル」の状態で早めに気づくことが重要です。
「視力低下」が認知症のリスクになる
視力低下が認知症のリスクになることが報告されています。
2024年に発表された「ランセット認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会」の報告において、視力低下が新たに修正可能な認知症のリスク因子(予防できる可能性のあるリスク)として加えられました。*1
未治療の視力低下がある高齢者は、視力低下のない高齢者と比べて、認知症を発症するリスクが高まることが、複数の大規模研究による分析から明らかにされているとあります。*1
今回の報告により、これまでの認知症の12のリスク因子(教育機会の不足、難聴、抑うつ、頭部外傷、運動不足、糖尿病、喫煙、高血圧、肥満、過度の飲酒、社会的孤立、大気汚染)に、「視力低下」と「高LDLコレステロール」が新たに加えられ、合計14因子となりました。*1
視力低下と認知症リスクの関係には、いくつかの要因が考えられており、ランセット委員会の報告書では、次のような可能性が挙げられています。*1
- ●視力低下の背景にある糖尿病などの病気そのものが認知症のリスクを高める
- ●白内障の手術によって、認知症の発症リスクが下がる可能性がある
- ●網膜と脳には共通する神経変性が起こり、視力の低下と脳の機能低下が同時に進行する可能性がある

また、韓国で実施された大規模な追跡調査では、視力障がいが重度の人ほど、認知症を発症する割合が高いことが明らかになっています。*1
視力低下が認知症の原因そのものである可能性や、視力と認知機能の両方に影響を与える共通の要因が存在し、その影響が大きいほど認知症のリスクも高まるという見方が示されています。*1
視力障がいの一歩手前、アイフレイルとは?
視力低下などの目の機能低下は加齢によっても起こります。加齢に伴う心身機能の低下が起こり、介護が必要になる前段階の状態はフレイルと呼ばれています。
アイフレイルは目のフレイルで、加齢に伴う目の機能の低下が起こり、視覚障がいの一歩手前の状態です。*2
40歳を過ぎると加齢によって目も衰え始め、次のような変化が現れることがあります。
光がまぶしく感じる
目が乾きやすい
小さい文字が見えにくい
目がゴロゴロする
目が疲れやすいと感じる
など
目の衰えがみられ始めのころは、自覚症状がない場合も少なくありません。しかし、目の機能低下が進むと、外出や仕事、家事といった日常生活に支障がおよぶ場合があります。視力低下は転倒リスクが10倍以上になるとも言われ、骨折などの大きなトラブルにもつながりかねません。*3
「視覚障がいにより日常生活が制限される」「転倒して骨折し、寝たきりになる」などが起こると、活動量の低下や社会参加の減少につながり、認知機能の低下を招くリスクも考えられます。
次のような加齢に伴って発症リスクが高まる目の病気も、アイフレイルの原因となります。
老眼:
加齢に伴う目の調節機能の低下で近くが見えにくくなる白内障:
水晶体が濁り、ぼやけて見える、かすんで見える緑内障:
視神経が障がいされて視野が欠ける糖尿病網膜症:
高血糖で網膜の血管が傷つき、視力が低下する、失明することもある加齢黄斑変性:
黄斑部(物を見る中心部分)に異常な血管ができて障がいを受け、ゆがんで見える、視野の中心が見えにくくなるなど
視力障がいは徐々に進行していき、失明する場合もあるので早めに気づくことが大切です。
視力低下を予防して認知症のリスクを軽減
目に負担をかけない生活習慣や定期的な検査でアイフレイルの早期発見につなげ、視力低下を予防しましょう。
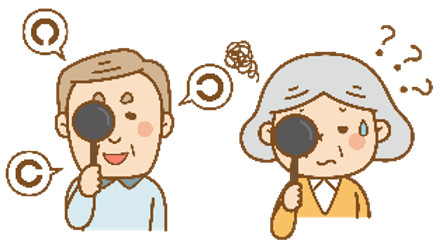
●目を酷使しすぎない
スマートフォンやパソコンを長時間使うときは、定期的に休憩を取り、目を休めましょう。
●紫外線対策をする
外出時にはサングラスや帽子を使い、目を紫外線から守ることが大切です。
●生活習慣病を予防・管理する
糖尿病や高血圧は目の病気と深く関係するため、定期的な健診と適切な治療が、目の健康維持につながります。

●定期的に眼科検診を受ける
とくに40歳を過ぎたら、定期的に眼科で目のチェックを受けましょう。
初期には自覚症状が出にくいため、早期発見・早期治療が重要です。
●アイフレイルチェックリストを活用する
アイフレイルのセルフチェックを活用し、気になる症状がある場合は眼科を受診しましょう。
【参照】40歳以上の人のためのアイフレイルガイド アイフレイルチェックリスト

アイフレイルは、加齢による自然な変化の一つですが、放っておくと視覚障がいだけでなく、生活の質の低下や認知機能の低下につながる可能性もあります。
小さな変化を「年のせい」と片づけず、日頃から目をいたわる習慣を持ち、定期的な眼科検診やセルフチェックを通じ、今からできるケアを始めてみませんか。
<参考文献>
-
*1 Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission Lancet 2008;404:572-628
*2 日本眼科啓発会議 40歳以上の人のためのアイフレイルガイド https://www.eye-frail.jp/wp-content/themes/theme_eyefrail/download/eyefrail_guide_240416.pdf
*3 厚生労働省資料 目の健康で転倒防止を https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001548624.pdf
- ※当記事は、『認知症予防習慣』コラムを引用して作成したものです。【2026 MCBI,Inc.】
- ※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。
- ※当記事の内容は、上記発行年月時点の情報に基づき記載しております。発行後の法令・制度等の改正、医療の状況の変化等は考慮しておりませんのでご注意ください。
掲載記事は、医療・医学に関する理解・知識を深めるためのものであり、特定の治療法・医学的見解を支持・推奨するものではありません。
また、診断や治療を必要とされる方は、適切な医療機関を受診の上、医師の指示に従ってください。
本情報に関して発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。


