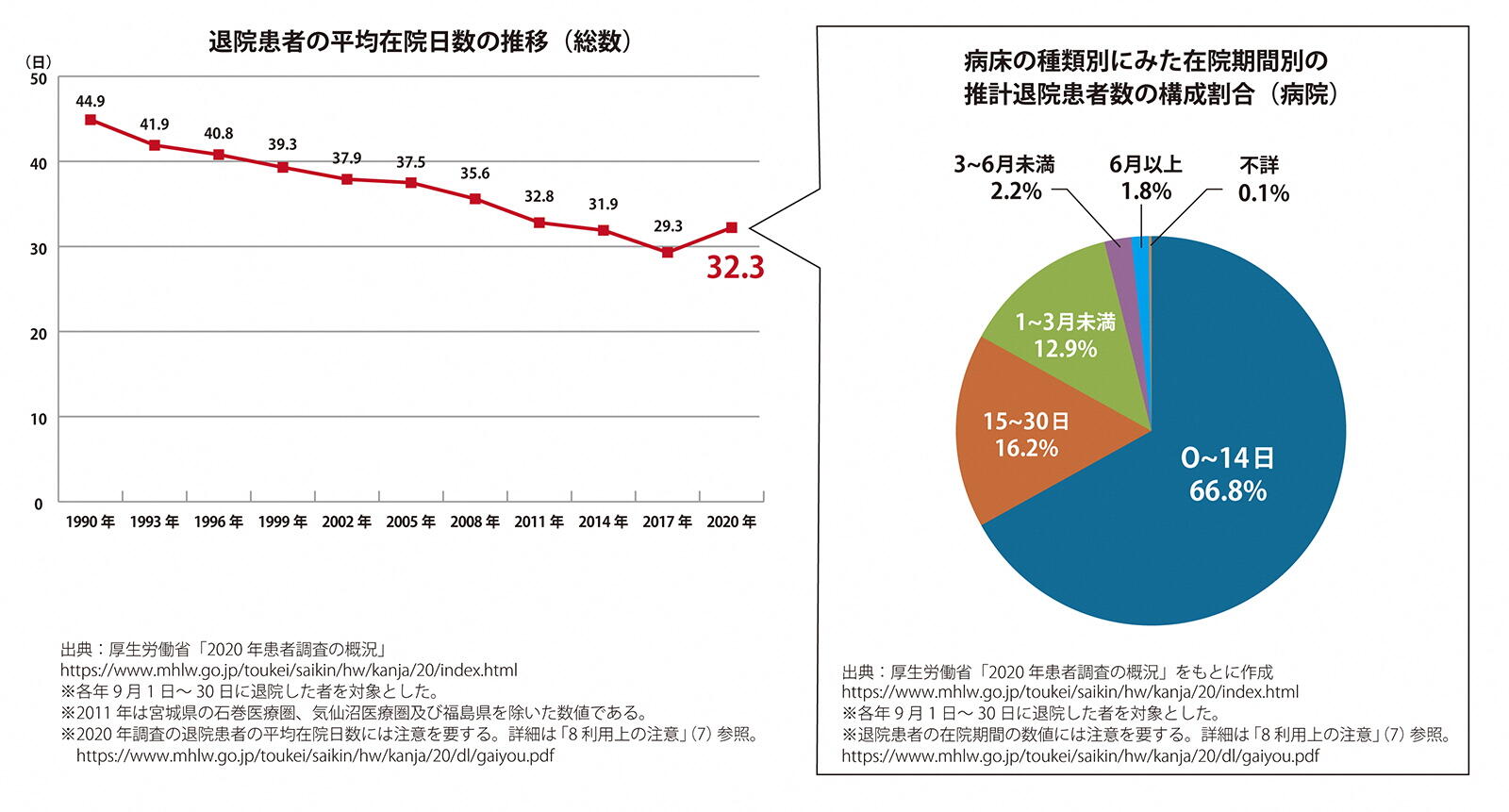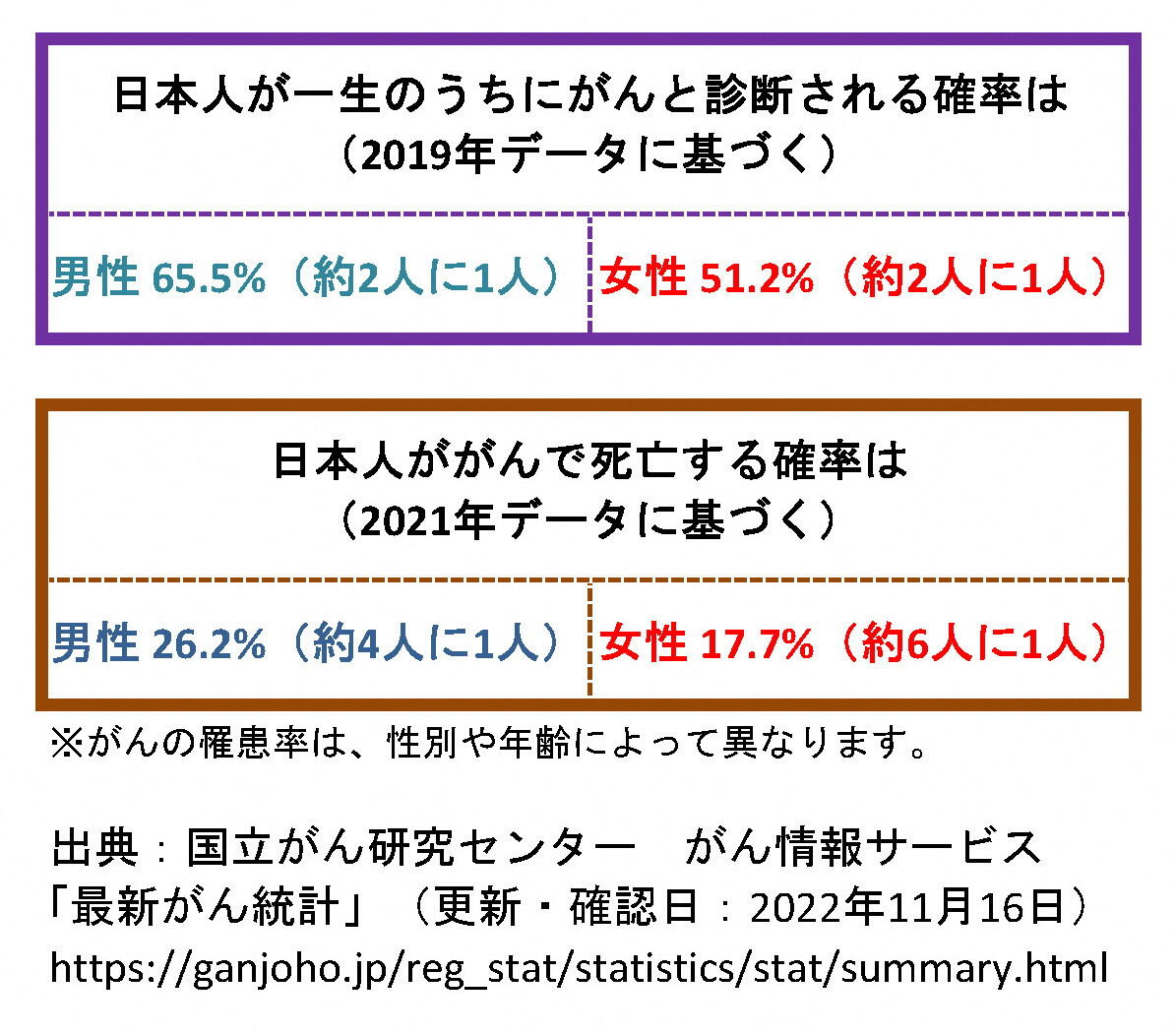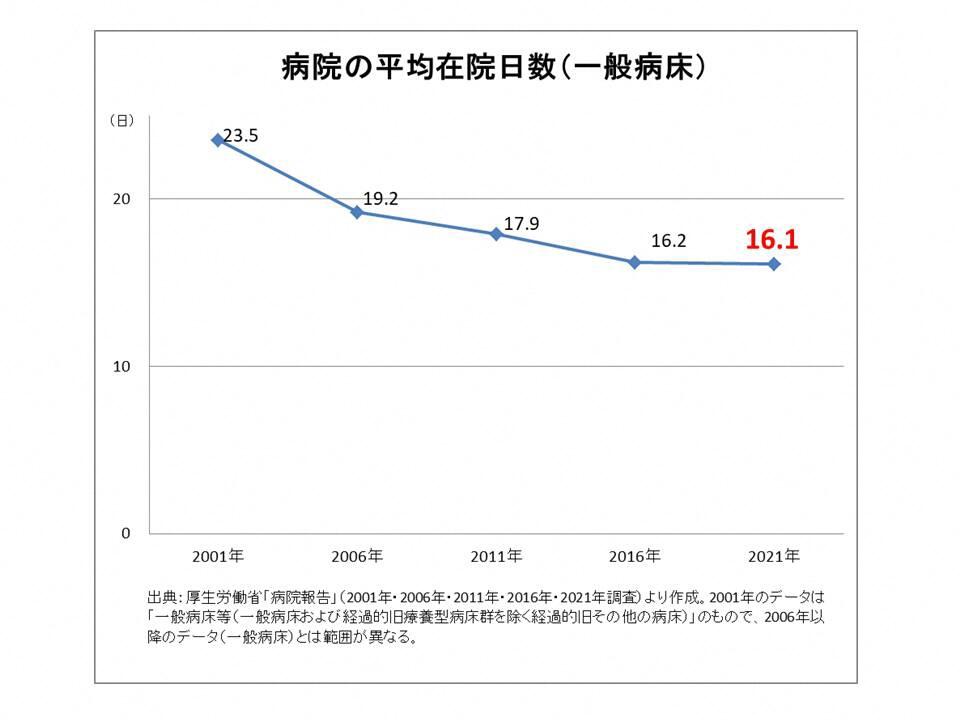素敵なうたをみつけよう~万葉集から学ぶ~
- 当社からファイナンシャルプランナーの先生等に依頼し、執筆いただいた記事を掲載しております。
- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。
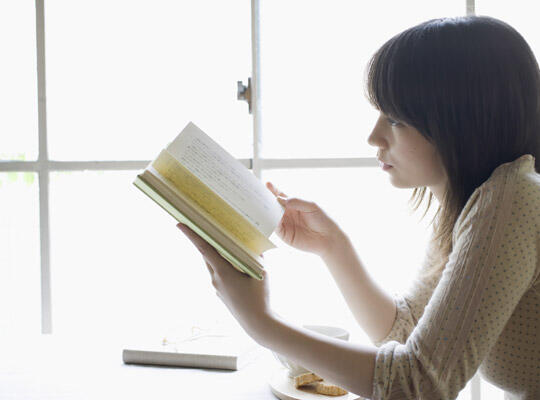
この時季、読書の秋を満喫されている方も多いのではないでしょうか。
今回は、秋らしく文学の香りがする内容でお届けしたいと思います。
文学といっても、古典文学。その中でも有名な「万葉集」についてです。
◆万葉集とは
「万葉集」というと、学生時代に一度は耳にした、あるいは学んだことのある書物ではないかと思います。
日本に現存する最古の和歌集で、全20巻から成り、約4,500首の短歌を中心とした古典詩を編集したものです。編者は大伴家持(おおとものやかもち)といわれていますが、複数の人が関わっていると考えられています。
日常におけるちょっとした感動や実感を率直に表現したものや、おおらかさや素朴な美しさを詠んだもの、また一方で、壮大で力強い格調を持つことも特徴としています(=万葉調)。
成立時期は奈良時代後期ですが、それより以前を含め約450年に亘って作られた歌が集められており、大きくは以下のような4つの時期に分かれるといわれています。
それぞれの期の特長、時代の目安、活躍したといわれる主な歌人は次の通りです
≪第一期≫ 集団的な儀式の歌から個性的な創作歌への移行期
620~670年代【飛鳥時代】
天智天皇(てんちてんのう)・天武天皇(てんむてんのう)・額田王(ぬかたのおおきみ)・鏡王女(かがみのおおきみ)・有間皇子(ありまのみこ)・藤原鎌足(ふじわらのかまたり)
≪第二期≫ おおらかで力強い万葉調の完成期
670~720年代【白鳳時代】
持統天皇(じとうてんのう)・大津皇子(おおつのみこ)・大伯皇女(おおくのひめみこ)・志貴皇子(しきのみこ)・穂積皇子(ほずみのみこ)・但馬皇女(たじまのひめみこ)・石川郎女(いしかわのいらつめ)・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)・高市黒人(たけちのくろひと)
≪第三期≫ 知的で繊細な和歌が生まれる万葉調の最盛期
720~730年代【奈良時代初期】
山部赤人(やまべのあかひと)、山上憶良(やまのうえのおくら)、大伴旅人(おおとものたびと)、高橋虫麻呂(たかはしのむしまろ)
≪第四期≫ 繊細で感傷的、表現に凝った万葉調の衰退期
730~760年代【奈良時代中期】
大伴家持、厚見王(あつみのおおきみ)・大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)・笠郎女(かさのいらつめ)・中臣宅守(なかとみのやかもり)・狭野弟上娘子(さののおとがみのおとめ)
◆万葉集のスター 額田王
額田王は、文字だけ見ると男性と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は女性です
熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
この歌をご存じの方は多いのではないでしょうか。
新羅と唐の連合軍に攻撃された百済を助けるため、斉明天皇と中大兄皇子、中臣鎌足らは、自らが率いる救済軍を朝鮮半島に派遣しようとします。
現在の愛媛県松山市の港から九州に向かうのですが、そのときの斉明天皇の心情を代わって詠んだものとされています。
月の光が輝く夜の海、ゆっくりと潮が満ちてくる美しい情景が見えるようですね。
「今は漕ぎ出でな」
これは、現代風にいうと「さぁ、漕ぎ出そう!」という意味です。
これから戦に向かう者たちを奮い起たせる雄壮さを感じさせます。
初期の万葉集の代表作の一つです。
◆額田王の有名な「恋の歌」
万葉集で歌われている内容は、
(1) 相聞歌(恋愛の歌)
(2) 挽歌(死を悼む歌)
(3) 雑歌(それ以外の歌。呪術的な歌や政治的な歌、自然を詠む歌など)
この3つに分けられます。
中でも、どうして「雑歌」に分類されているのか不思議に思うところも多い次の歌。これはまさしく「恋の歌」で、万葉集の中でもよく知られています。
茜さす 紫野ゆき 標野ゆき 野守は見ずや 君が袖振る
「茜さす」は紫にかかる枕詞で、美しい表現です。
夫である天智天皇とその一行が薬(薬草)狩りに出かけた紫草の生えている御料地で、行ったり来たりして袖を振っているあなた、野の番人に見られてしまいますよ、という意味です。
袖を振っているのは、後の天武天皇である大海人皇子(おおあまのみこ)で「額田王の元夫」です。袖を振るという行為の意味は諸説ありますが、好意を示していることを表しているのに間違いないでしょう。
この歌の返歌として、大海人皇子は次のように歌っています。
紫の にほへる妹を 憎くあらば 人妻故に 吾恋ひめやも
紫草のように美しいあなたを憎く思っていたら、今は人妻となってしまった。そんなあなたをどうして愛せましょう、という意味です。
直訳すれば「今でも好きです」ということです。
道ならぬ恋を表しているものの、こうしたやりとりは実は宴の中で行われたものです。おそらく、“大人の嗜み”といったところだったのでしょう。
恋や愛という揺れ動く感情の機微を表した歌は、心魅かれる美しい表現が多くあります。ひとつずつ鑑賞してみると、彼らの背景や物語が見えてきて、現代と変わらない感情の発露にぐっと引き込まれるはずです。
上記で紹介したような楽しみ方以外に、草花など自然について歌われているものを探して、日本古来の草花のたたずまいを感じたり、防人の歌(今の九州に“防衛隊”として駆り出された関東地方の民衆の歌ったもの)から、現代のビジネスマンに重なるものを感じたりすることも、また味わい深いものです。
◆歌の探し方・解説本の選び方
すぐできる方法としては、インターネットで上記にあげている歌人の名前を検索してみるのもおすすめです。
また、書店に行くと、学術書から読みやすい解説本まで数多く出ています。興味のある内容や理解度に合わせて選ぶことができますので、ぜひ足を運んでみてください。意外とわかりやすいのが受験生向けに書かれたものです。これから色々学びたいという「初心者」の方には特におすすめです。
万葉集の解釈は千差万別です。
サイトでも書籍でも、複数の解釈を読んでみるとよいでしょう。昔はよくわからなかったものが見えてきたり、面白みを感じたり、それぞれに楽しめると思います。
古代へ想いをはせながら、深まる秋をお過ごしください。
ライター(教育) 石井悦子