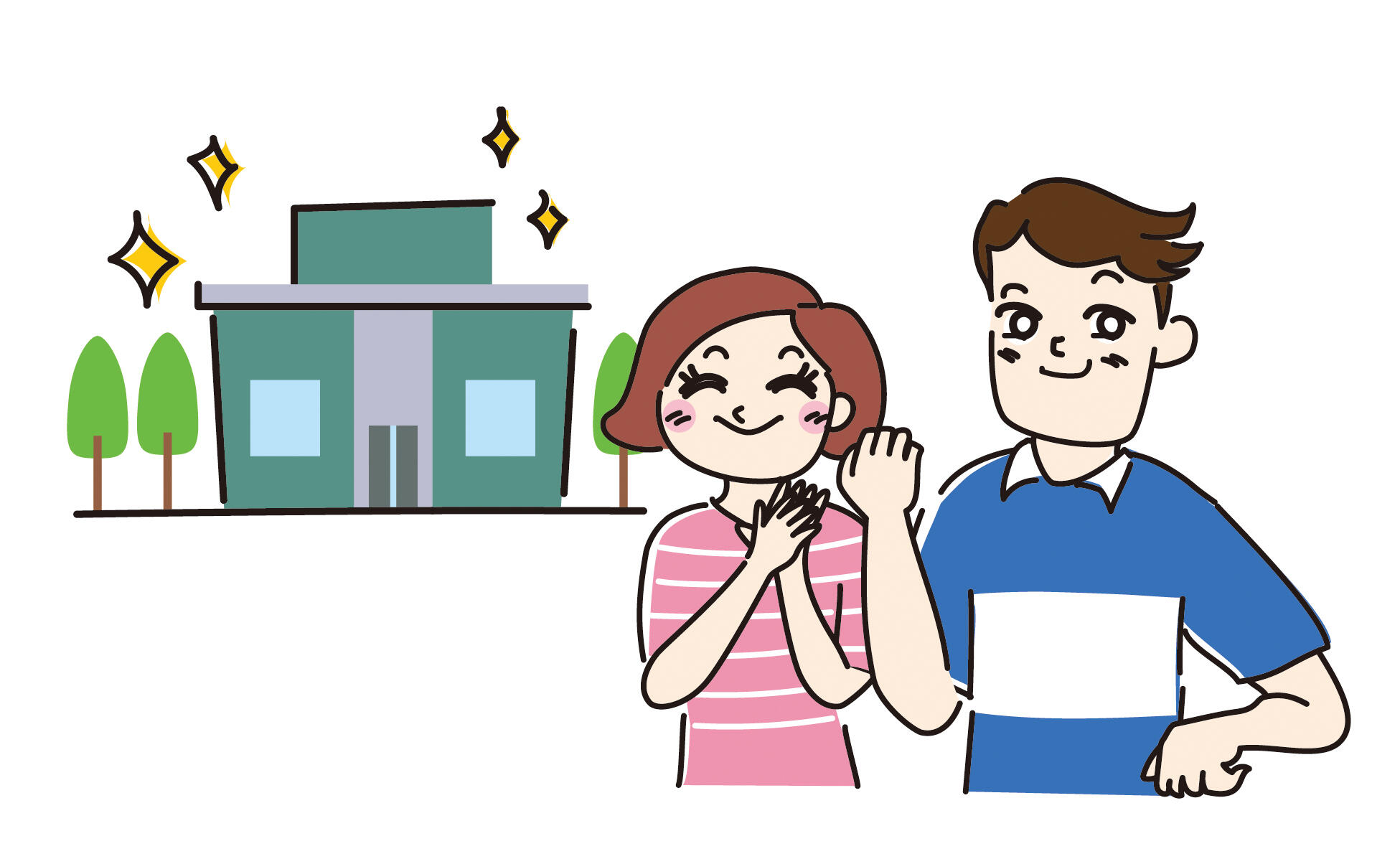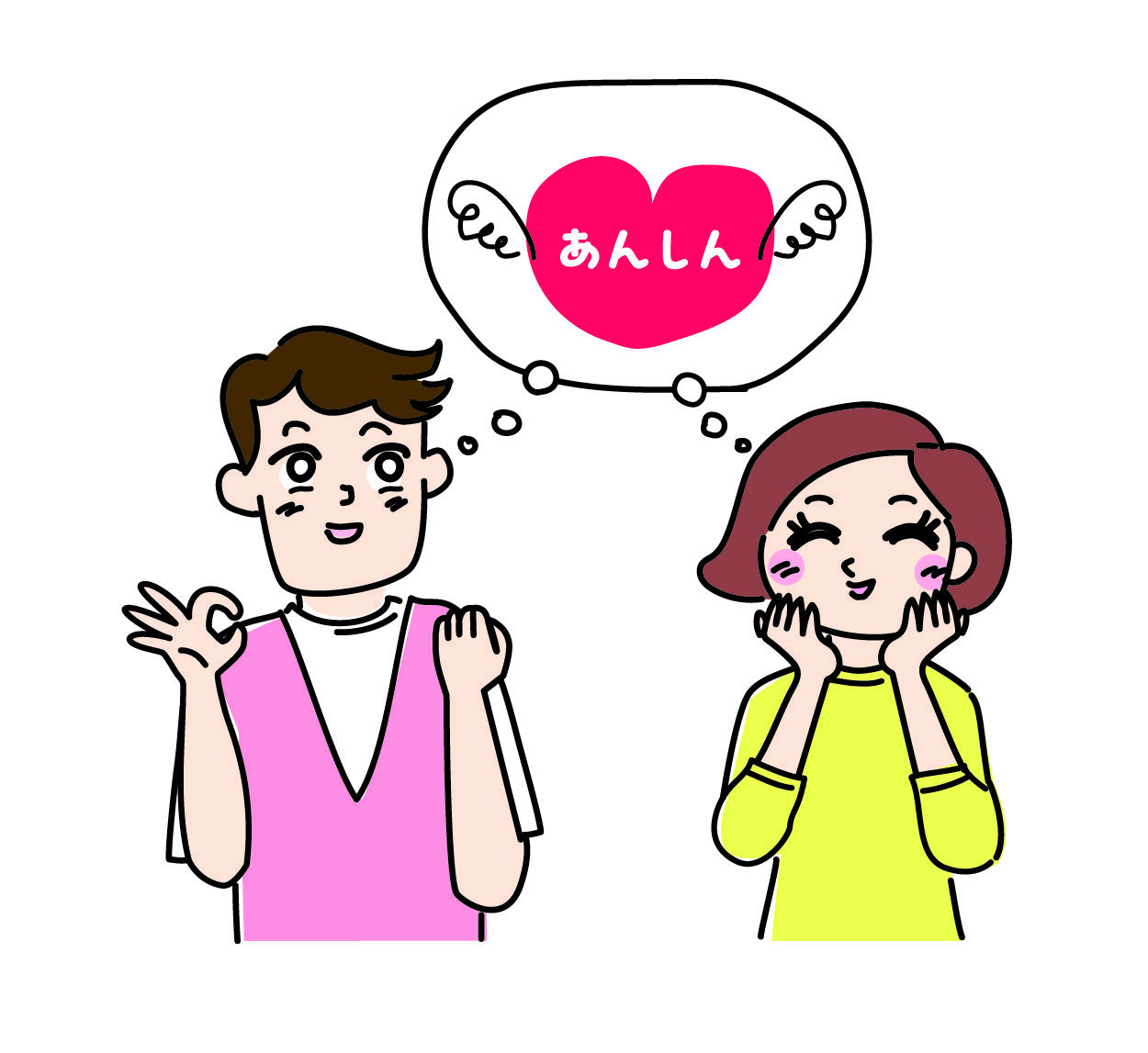知っトク!相続に関わる民法改正のポイント
- 当社からファイナンシャルプランナーの先生等に依頼し、執筆いただいた記事を掲載しております。
- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

2018年7月に民法(相続関係)が改正され、2019年から随時施行されます。相続が発生した後でも、残された配偶者が安心して暮らしていける策なども織り込まれています。改正により、どのような点がどのように変わるのか、5つのポイントを整理しておきましょう。
1・自筆証書遺言が使いやすくなる(2019年1月13日から)
全文自筆しなければ無効だった自筆証書遺言が、財産目録のみ自書でなくてもよくなります。具体的には、財産目録をパソコン等で作成してプリントしたり、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付して、自筆証書遺言を作成することができるようになります。財産目録以外の部分は、これまでと変わらず手書きしないといけません。
また、2020年7月10日からは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度も創設されます。自筆証書遺言には、見つからない、捨てられる、書き換えられるなどのリスクがありましたが、それが解消され、より安全に利用できるようになります。また、検認も不要になるためより使い勝手がよくなります。
2・遺産分割前でも預金の引き出しが可能に(2019年7月1日から)
これまでは、亡くなった人の預貯金を、遺産分割前に相続人が引き出すことはできませんでした。分割協議が終了するまでは、口座が凍結されてしまうからです。そのため、当面の生活費や葬儀費用、亡くなった人から引き継いだ債務の返済など、支払わなければならない資金があっても、亡くなった人の預貯金を使うことができません。保険に入っていなければ、相続人が一時的に立て替えるなどしていました。
今回の改正では、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められることになりました。また、各口座ごとに法定相続分の1/3までの預貯金(最高150万円まで)については、遺産分割協議が調う前でも引き出せるようになります。
3・結婚20年以上の夫婦間の住宅の贈与は持戻し不要(2019年7月1日から)
結婚20年以上の夫婦の一方が、住んでいる家を遺贈または贈与した場合、2,000万円までは控除を受けることができ、非課税で贈与等ができます。しかし、これまでだと、原則として遺産の先渡しを受けたものとして扱われ、配偶者が最終的に取得する額は贈与等がなかった場合と変わらない結果になっていました。
しかし今後は、「持戻しの免除」の意思表示があったものと推定し、遺産分割の際には「特別受益」として扱わず、つまり、持戻しをせずに計算することになり、配偶者により多く相続財産が残せることになります。
例えば、相続人が妻と子の2人で、相続財産が自宅(評価額2,000万円)と預金(3,000万円)だったとします。夫婦は結婚20年以上で、夫は亡くなる前に自宅(評価額2,000万円)を妻に贈与したとします。夫が亡くなると、改正前は、法定相続分通り1/2ずつ分割すると、生前贈与分を持ち戻した場合、妻は自宅2,000万円+預金500万円、子が預金2,500万円でしたが、改正後は妻が自宅2,000万円+預金1,500万円、子は預金1,500万円となります。妻には助かる変更ですね。
4・介護・看病に貢献した親族は金銭請求が可能に(2019年7月1日から)
今回の改正では、相続人ではない親族、例えば嫁や婿、甥や姪などが無償で介護や看病に貢献した場合には、「特別寄与者」として、相続人に対し金銭(特別寄与料)を請求できるように変わりました。これまでは、被相続人と養子縁組をするといった方法を取らない限り、報われることはありませんでしたので、大きな変化といえます。
5・「配偶者居住権」が新設され登記も可能に(2020年4月1日から)
「配偶者居住権」とは、配偶者が被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、無償で使用することができる権利です。具体的には、建物に関する権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」とに分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を、ほかの相続人が「負担付きの所有権」を取得します。あるいは、遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
一般の所有権と違って売却や貸与はできない分、評価額は安くなるものの、配偶者が自宅に住み続けることができて、しかも、預貯金などの財産も多く取得できるメリットがあります。配偶者にとっては、その後の生活の安定を図ることができます。
例えば、相続人が妻と子の2人で、相続財産が自宅(評価額2,000万円)と預金(3,000万円)だったとします。妻が家に住み続けるには、法定相続分通り1/2ずつ分割すると、妻は自宅2,000万円+預金500万円、子が預金2,500万円となり、妻の老後資金が不十分です。改正後は、仮に配偶者居住権の評価額が1,000万円だったとすると、妻は「配偶者居住権」+預金1,000万円を相続できます。
おわりに
民法改正(相続関係)のうち、5つのポイントを取り上げましたが、施行時期は一部を除いて2019年7月です。家族で相続について話し合う際には、今後の変化も頭に置くことも大事です。
<参照>